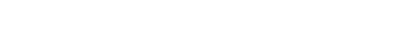本日は
「肩が痛くて挙がらない」
という方に聞いて欲しい内容です。
目次
- ■組織損傷ではない前提
- ■運動連鎖を使う
- ◎肩を挙げる際の体幹の動き
- ■できる動作を把握し反復
- ■自源抑制・自動抑制
- ■筋肉の緊張をほぐす
- ■これくらい変わりました
- ■まとめ
■組織損傷ではない前提

腰痛や肩こりと同じ様に
肩が痛いと言っても色々な痛みがあります。
肩の腱板が損傷しているケース、
断裂しているケース、
何かしらの軟部組織損傷、
筋肉や神経的な由来
石灰化
などなど。。。
今回のお話は
あくまでも
組織的な損傷が無い場合に有効です。
神経(腋窩神経や筋皮神経など)の圧迫や
筋肉が痛んでいる等であれば
効果を期待できますが、
さすがに腱板自体が損傷していたら
まずは安静が重要です。
■運動連鎖を使う
基本的にどこかの骨や関節が動くと
その動きに伴い、
他の関節も一緒に動く運動連鎖が生まれます。
例えば、
しゃがみ込む際には
膝が曲がるにつれて
大腿骨(太ももの骨)が
外旋(外に捻じれる)されます。
また、立ち上がる時には
膝が伸びますが
その際大腿骨は内旋されていきます。
※クローズドチェーンと言ったりします(^^

といった具合に
どこかの関節が動くと
その近くの関節や骨も
一緒に連動して動きます。
この働きを使います!
◎肩を挙げる際の体幹の動き
ここからが重要な実践活用編です!
下記を試してみて下さい!
●右肩を前へ挙げる場合(屈曲)
体幹部(胴体)を左側へ捻りながら挙げる。
●右肩を横に挙げる場合(外転)
体幹部(胴体)を右へ捻りながら挙げる。
●右肩を後に挙げる場合(伸展)
体幹部(胴体)を右に捻りながら挙げる。
●右肩を前に挙げる場合(屈曲)
手のひらを上に向けながら挙げる
(前腕回外・上腕骨外旋)
そして全ての動きを
『肩甲骨から動く意識』
を持ってください!
これ👆メッチャ重要です!!!
これだけで多少の変化は期待できます。
👆
■できる動作を把握し反復
どこまで挙げると痛いのか、
どの角度が痛いのか等
痛み方を自分で理解、把握をしましょう!
で、
先ほどの運動連鎖を使いながら
痛みが出ない範囲、角度で
何度も何度も動かしてあげましょう!
脳へ「痛くない」
というインプットをさせる事が大切です。
※良い動きの上書き保存的な!
■自源抑制・自動抑制
少し難しい話ですが、
自源抑制は
「出した瞬間にブレーキがかかる」
自動抑制は
「出した結果を見てブレーキをかける」
という意味があります。
どちらも、
暴走を防ぐために体に備わってる
「自己コントロールシステム
と覚えておきましょう。
ここで試して欲しいのが、
肩を下げる力と
それを止める力を
拮抗させる事です。
例えば、
右肩(腕)を下げる場合、
左手で右腕が降りてこない様に
制御(堪える)させるイメージです。
こんな感じ↓
右手の下す力と
左手の止める力の勝負ですね!
もちろん痛みが出ない範囲で実施しましょう!
※他にも振り子運動などが良い👇
YouTubeチャンネル第2回「振り子運動」 おうちでできる簡単ストレッチ 肩関節周囲炎(五十肩)の運動療法
■筋肉の緊張をほぐす
肩を動かす際に重要となる
●鎖骨(鎖骨の上下)
●首(胸鎖乳突筋)
●肩甲骨周辺
をしっかりほぐしましょう!

よく筋膜リリースなんて言ったりしますが、
骨と筋膜の滑走性を良くし
動きをスムーズにさせます。
これらの緊張が解けるだけで
肩は挙がりやすくなる事があります。
特にほぐし方に拘る必要はありません。
痛みが出ない範囲で行う事ですね!
■これくらい変わりました
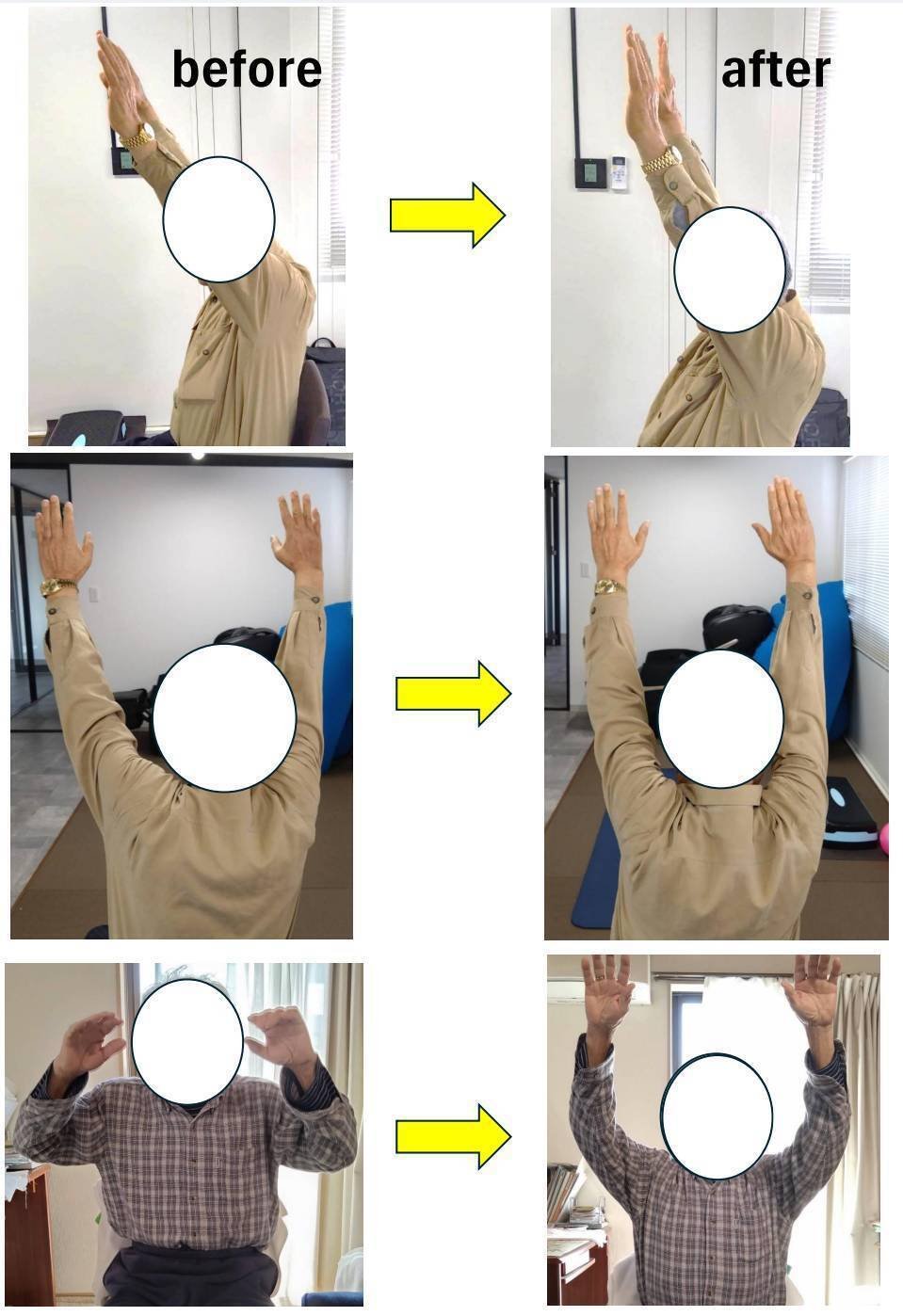
■まとめ
●組織損傷の場合は安静から
●運動連鎖を使って肩を挙げる
●全て肩甲骨から動く意識で
●できる動作を理解し反復する
●肩を下げる動作に抵抗を
●鎖骨、首、肩甲骨周辺をほぐす
もちろん
肩痛に対するケアは
これだけではありませんが、
まずはこの6つを意識してみて下さい!
最後までお読みいただきありがとうございます(^^